KCG10月度定例セミナーの講師は、マリア訪問看護ステーション 代表の松栄貴子(まつえ たかこ)さんです。
2025年2月に起業し、5月に開業したばかりのこの事業所は、医療と福祉の狭間に落ちた人々に寄り添う訪問看護の実践の現場です。
現在26年のキャリアを活かし日々奮闘する松栄さんの足跡と想い、その背景にあるドラマをお聞きしました。

生活支援から医療へ、看護師としての道を歩み始める
松栄さんの職業人生の出発点は介護福祉士でした。
高校卒業直後、人の生活を支えたいという想いから介護福祉士の道を選び、特別養護老人ホームでの勤務を始めたのです。
ところが現場で気づいたのは、「生活支援だけでは足りない」という違和感でした。
医学的な知識があれば、利用者さんのためにもっと多くのことができるのではないか—その問い自体が、進路変更の決断を促しました。
看護学校へ進学し、試験に合格した後、病院や老人保健施設での看護業務に従事する日々が始まります。
26年間、患者さんに向き合う現場の第一線で、注射をして、点滴をして、話に耳を傾けてきました。
結婚し、子ども2人を育てることになり、特に上の娘の子育てに追われていた時期、親としての時間と仕事を両立させたいという願いから、
心身に障がい者を抱える人々の支援施設が運営する訪問看護職への転職を決めたのです。

訪問看護の現場で見えた、医療福祉の狭間にいる人たち
訪問看護師として働き始めた松栄さんは、最初の3年間、精神科訪問看護に集中し、患者さんと向き合いながら少しずつ信頼を重ねていきました。
その過程で管理補佐、管理者、主任へと昇進し、新規事業の立ち上げにも関わり、営業も担当し、複数の事業所を経験していきます。
ところが、精神障がい者支援の現場で次々と出会わされるのは、生活困窮者、刑務所経験者、触法障がい者という社会から敬遠される人たちでした。
彼らを医療や福祉サービスへつなげようと試みても、行政からは「そのような事例は前代未聞です」と断られる繰り返しで、医療、福祉、行政という縦割りシステムの狭間に落ちた人々が救われない現実に直面することになったのです。
医療福祉の対症療法的なアプローチの限界を何度も体験する中で、松栄さんの心は段々と揺さぶられていきました。
前職の経営陣との方向性も、次第にズレていくのを感じました。
現場の課題を見ている者と、管理層の目線は異なり、自分が心から実現したいこと、
それと組織の向かう方向との乖離がだんだんと大きくなっていった違和感が、昨年の年末には確信へと変わったのです。
「自分で動く必要がある」という想いは迷いなく、年明けからの実行へ向かうことになりました。

ゼロからのスタート:資金繰りの危機を乗り越えた経営の現実
活字で学ぶことが得意ではない松栄さんは、YouTubeの動画から企業について学び始め、
訪問看護には常勤換算で2.5人以上の職員が必須という条件を知り、一人では実現できない事業であることに気づきました。
前職の同僚に声をかけると「一緒にやりましょう」という返事が返ってきて、二人で立ち上げる計画が動き出したのです。
1月から準備が本格化し、電子カルテメーカーの支援を受けながら法人設立の書類を整え、融資の打ち合わせも同時並行で進んでいきました。
2月中に事務所を確保し、3月末までに行政への指定申請書類を提出しなければ、5月1日の開業には間に合わない、
という限られた時間軸の中での綱渡りが始まったのです。
「2月と3月は、本当にプレッシャーと葛藤の日々でした」という回顧は、その時の緊張感を今も伝えるものです。
指定申請が承認されると、また別の波が押し寄せてきました。
毎日かかってくる営業電話、ホームページ制作、セキュリティ設備投資、事務用品の手配—やることは際限なく続いていったのです。
そんな中で訪れた最大の試練が融資手続きの遅延でした。
数字が弱かった松栄さんは融資書類の修正に予定以上の時間を要し、結果として融資は予定より1ヶ月遅れてしまったのです。
その遅延がもたらしたのは経営に対する致命的な打撃で、自己資金は底をつく寸前に追い込まれ、
リース会社からの請求書がやがて督促状へと変わっていく恐怖を経験しました。
「会社として毎日なんかしらの支払いがある」という現実に直面し、26年間患者さんに向き合ってきた松栄さんは、
突然経理や財務という全く別の世界に放り込まれてしまったのです。
「右も左も分からない状態で、毎日が本当に大丈夫なのか、と思っていました」という当時の感覚は、今でも完全には消えていない実感だと言います。
分からないことばかりなのに、毎日何とか進んでいく中で生まれた心構えが「できないことを、できるにしよう」というスローガンでした。
その想いが毎日の学習と改善を促し続け、「できないをできるに変える」ことが松栄さんにとって最大の目標であり、同時に楽しみでもあるという状態になっているのです。

業界の課題を理解し、敢えて誰もやらない道を選ぶ
訪問看護業界全体を見ると、看護の現場での経験は豊かでも、経営数字に関しては課題を抱える事業所が多いという傾向が見られます。
創業計画は大体計画通りに推移し、登録者数も予定通り増えていたものの、金額面が甘かったと松栄さんは反省しています。
訪問看護は国からの加算額が決まっている制度で、自由に金額設定できない事業体系の中では、
売上を増やすには件数を増やすしかない制約があるのです。
「最初から完璧な経営者はいません。今、私に必要なのは『簿記』と『数字』です」という言葉は、
謙虚さと決意が同居した境地を表しており、松栄さんは日々その習得に向け奮闘しています。
新規参入事業所の戦いは本当に苦しいものです。
医療機関からの指示書がなければサービス提供は収入化できない制度設計で、ほとんどの事業所は医師の指示書を待つ受け身の状態にあります。
太いパイプを持つ大手には仕事が自動的に降ってくる構造で、小さな新規参入事業所にはそういう優位性がないのです。
では、どうするのか—松栄さんの答えは「他人のやりたがらないことをやる」というものでした。
誰もやっていないことに本当のニーズが潜んでいるという戦略は、医師の指示書を待つのではなく、
医療や福祉サービスが必要でありながら受けていない人にこちらからアプローチすることです。
その人を医療へ、福祉へとつなげ、相談支援専門員をつけ、
複数の視点からケアを支える手段を整えることが松栄さんたちの本当の役割だと考えているのです。

146万人の人たちへの想い、社会を変える構想
日本の引きこもり者は15~64歳の間で推計146万人、生産年齢人口の約2パーセントに相当します。
医療や福祉を必要としながら、それを受けられずに路頭に迷う人たちがたくさんいるという現実は、松栄さんが何度も見てきた経験でした。
「病気の段階で治療していれば、ここまで症状が悪くなることもなかった」という、もしもの人生を歩んでいる人たちの記憶が、
今の実践を支える源泉になっているのです。
社会福祉協議会や行政職から、住居確保が必要な方々の相談が増えてきました。
訪問看護は医師の指示書さえあれば収益化できますが、松栄さんの関心は指示書の先にあり、
医療機関へのアプローチ、福祉サービス導入、相談支援専門員配置といった、その人を中心に置き複数の視点から支える構造づくりにあります。
「何をやってるんですか」と聞かれることもあり、周囲には理解されない道を歩んでいる実感を持ちながらも、
それでもやり続けることに意味があり、少しずつ浸透していくはずだという信念を持ち続けているのです。

人として、経営者として大切にしていくこと
行政や福祉関係者から敬遠される人たちがいます。
犯罪歴のある人、生活保護受給者、触法障がい者—彼らは時に「人として」扱われないことがあります。
しかし松栄さんの姿勢は異なります。
「その人も、間違いなく人間です。だからこそ、人として接する必要があるんです」という言葉に込められた信念は揺るがないものなのです。
看護師としてのポリシーはシンプルで、利用者さんと向き合い理解することから始まります。
その人がどんな人なのか、何に困っているのか、どんな人生を歩んできたのか—第一印象で判断するのではなく、
「この人はどんな人だろう」という興味から始まり、会話の中で少しずつその人が見えてくるのです。
そこから信頼関係が生まれ、「相手の話に耳を傾け、ありのままを受け入れる」ことが大切だと松栄さんは強調しました。
ダメだと決めつけるのではなく、そうなるまでの背景や理由を理解する姿勢の中に、信頼が育まれるものなのです。
訪問看護というと高齢者ケアのイメージが強いかもしれませんが、松栄さんたちが中心に見ているのは、
発達障がい、知的障がい、精神障がいを抱える人たちで、その中には触法障がい者も含まれています。
しかし、松栄さんたちは同じように受け入れ、常に学ぶ姿勢を忘れず、
死ぬまで勉強し続け、日々の出来事の中に学びを見つけ、人間力を高めることを常に意識しながら実践を続けているのです。
「一歩先は無限大の可能性がある」。
これが松栄さんが最後に何度も伝えたかった言葉です。
「どうせ無理」という決めつけで試す前に諦める虚しさを松栄さんは知っています。
「医療や福祉に貢献して、愛情が溢れるような世界を作ること」—松栄さんが何度も繰り返したこの言葉は、職業的な目標ではなく、死ぬまで続く人生のテーマなのだと感じさせられました。
2月の決意からわずか数ヶ月、融資の課題や資金繰りの危機を乗り越えた松栄さん。
その姿勢と実践は確実に一歩一歩前へ進み続けているものです。
医療福祉の狭間に落ちた人たちへの想い、そして業界そのものを変えたいという松栄さんの想いが、これからどのような実を結ぶのか。
その歩みは、確実に何かを変え始めているに違いないのです。

懇親会
今回も、定例会後に懇親会を行いました。その一幕をご紹介いたします。









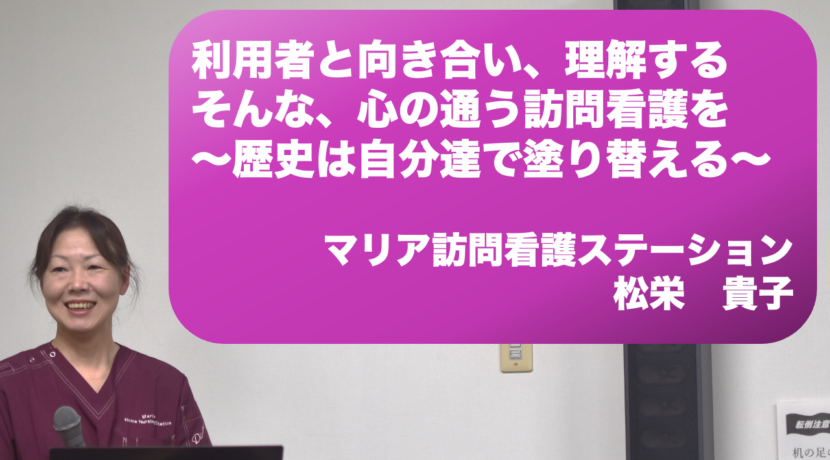

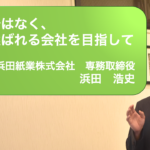
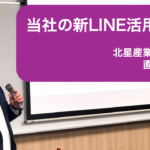



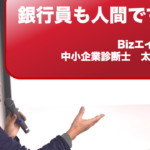
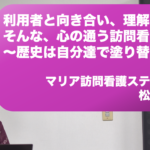
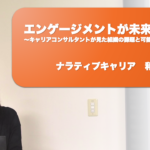
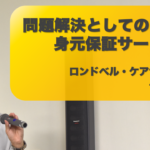







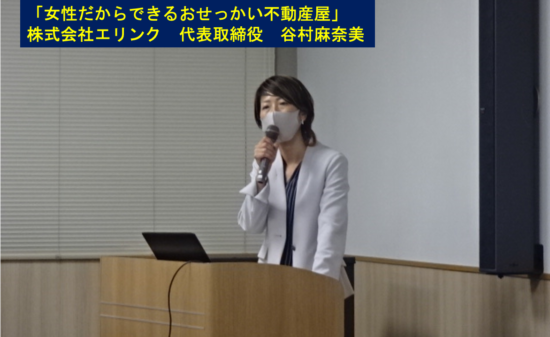


 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。