KCG9月度定例セミナーの講師は、ナラティブキャリアの和田矩子(わだ のりこ)さんです。
2021年10月にも登壇していただきましたが、その時は障がい福祉の専門家として、今回はキャリアコンサルタントとして新たな視点でお話いただきました。
この4年間で個人事業主として独立を果たし、金沢を拠点に活動を続けてきた彼女が語る組織の課題と可能性。
人材不足に悩む多くの企業にとって希望の光となることでしょう。

「せともの」の町から始まった人生の転機
愛知県瀬戸市で生まれ育った和田さんの人生は、20歳での大きな決断から始まりました。
スキューバダイビングインストラクターになるため沖縄に飛び立った彼女。
1年間無給で働き続ける日々でした。月5000円の食費だけで生活する過酷な環境。
それでもお客様と海の感動を分かち合う仕事にやりがいを見出していたといいます。
この沖縄での体験こそが、後に彼女が提唱する「内発的動機と外発的動機のバランス」理論の原点。
やりがいだけでは食べていけないが、やりがいなしでは生きていけない。
この実感が現在のキャリア支援の根幹を成す哲学となっています。
30歳で結婚を機に石川県に移住した和田さん。
人材紹介会社で営業兼コーディネータとして働き始めました。
両親も能登島へ移住するという家族ぐるみの大移動でしたが、その後離婚を経験。
シングルマザーとしての人生がスタートしました。
人材紹介会社での経験が、彼女に「人の人生のターニングポイントに関わる仕事」の魅力を教えることになります。その後は障がい福祉分野へ。
就労移行支援事業所で管理者として働き、軽度の知的障がいや精神障がいのある方々の就職支援に携わりました。
多様な働き方への理解を深める貴重な機会となり、この経験が現在の活動基盤を形成しています。

40歳での独立〜全てはハングリー精神から〜
40歳という節目の年に、和田さんは個人事業主として独立する決意を固めます。この決断の背景には3つの大きな要因がありました。
まず、シングルマザーとして会社員の収入だけでは不十分だという経済的な現実。子どもたちを育てていくためにも、思い切った決断が必要でした。
次に、20歳で沖縄へ、30歳で石川へと環境を変えてきた自分自身のパターンへの気づき。
10年ごとに新しい挑戦をしてきた人生を振り返ると、40歳という節目も同様に大きな変化の時期として捉えられたのです。
子どもたちの入学・卒業時期とも重なり、家族全体での新たなスタートとしても最適なタイミング。
そして最後に、将来への危機感。
「気づいたら自分のキャリアがない」という状況だけは避けたい。
この強い想いが独立への背中を押したのでした。
和田さん自身の言葉を借りれば、「全てはハングリー精神から」の独立です。
現在は石川県を拠点にキャリア支援を専門として活動。
就職支援・セミナーの開催、法人個人のキャリアコンサルティング、キャリアコンサルタント養成講座の講師など、
多岐にわたる取り組みを展開されています。

令和時代の働き方革命〜3低が示す新しい価値観〜
昭和から令和へと変化する働く価値観の本質を解き明かした今回のセミナー。
和田さんが提示した切り口は実にユニークでした。結婚相手に求める条件の変遷を通じた分析です。
昭和時代は「3高(高学歴・高収入・高身長)」、平成時代は「3平(平均的収入・平凡な外見・平穏な性格)」、そして令和時代は「3低(低姿勢・低依存・低リスク)」。この変遷が何を物語っているのか。
女性の社会進出により、男性に求めるものが「経済力」から「安心感・対等性」へシフト。
同様に、仕事に求める条件も昭和の「安定・権威・待遇」から、平成の「そこそこ・安心・平凡でもいい」を経て、令和の「低リスク・低依存・心理的安全性」へ。
時代とともに価値観の根幹が変わったのです。このことは、仕事の価値観とも関連している、と和田さんは語ります。
注目すべきは、安定している会社を求める若者が5割から7割に上昇している事実。
しかしその「安定の中身」が根本的に変化している点です。
経済的安定よりも、職場の風通しのような精神的安定こそが重要視される時代になっています。
昭和時代の価値観を象徴するのが「ロイヤリティ(忠誠心)」でした。
給料・終身雇用による経済的安定性が優先され、組織への忠誠が前提となる経営トップ主導の一方通行の関係性。
多少の不満があっても会社のために我慢する文化が当たり前だったのです。
対照的に令和時代に求められるのは「エンゲージメント(共に成長)」。
フラットな組織構造の中で心理的安全性が確保され、働きがいや成長実感を重視する双方向の関係性が特徴となっています。
転職も一般的になり、単に長く勤めてもらうだけでは人材定着は困難。
「企業が求める人材」と「個人が求める企業」を両立させる「すり合わせ」の視点こそが重要なのです。

採用から定着まで〜実践的な組織づくりの手法〜
採用から定着までの実践的なアプローチについて、和田さんの提案は明日から使える知識の宝庫。
表面的なスキルマッチングを超えた価値観の適合性を重視する採用戦略が印象的でした。
面接で確認すべき「仕事への価値観」として推奨されているのが、「求職者が仕事において大切にしていることは何か」という質問です。
会社側が大切にしていることとのすり合わせを行う手法。シンプルながら効果的なアプローチといえるでしょう。
求人票改善のポイントも具体的。
キャリアパスの具体化、異動の有無、新しい業務への挑戦可否を明記することが重要です。
SNS発信では動画活用の重要性が強調されてきました。
今の時代、求職者は必ず企業情報を検索している。この前提に立った情報発信が求められています。
職場見学・体験会については、発想の転換が必要。単なる「見せる場」ではなく「関係を築く場」として活用し、入社後の道筋をイメージしてもらうことが大切です。
求人段階では「子どもの熱で急な休みが取れるか」といった本音のニーズを引き出すことも重要なポイントとして挙げられました。
社内施策については二つの側面から。
制度的・ハード的な部分として成長機会(キャリアパス)の設計。
そして感情的・ソフト的な部分として感謝やねぎらいの言葉が関係性を変える力を持っている。
この指摘は多くの参加者にとって新鮮だったようです。
和田さんは会社組織を体の組織に例え、「体の変化に気づきにくいステージ1」の危険性を指摘。
相談なく突然辞めてしまう社員の存在は、組織の健康状態に問題があることの表れです。
人材不足や人材育成に悩みを持つ企業が7割を超える現在、定期的な組織診断の重要性が高まっています。
セミナー後には活発な議論が展開されました。
特に印象的だったのが、40代で未経験業界への転職を希望する相談者への対応についての質問です。
和田さんは「まず否定はしない」という基本姿勢を明確に示し、なぜそう思うようになったのか経緯を聞く大切さを説明。
今の会社でその職種に活かせる経験を積めないか一緒に考えるという段階的なアプローチを提案されました。
このような丁寧な対応こそが、キャリア支援の本質を表していると感じられた瞬間でした。

未来への展望〜セルフ・キャリアドックと診断ツールの可能性〜
キャリアコンサルタントの活動領域は多岐にわたります。
学校教育、就職支援機関、企業、医療・福祉、公共サービス(ハローワークなど)の5つの分野です。
2016年4月施行の職業能力開発促進法において国家資格と定められたキャリアコンサルタントから、キャリアコンサルティング2級技能士、
さらに1級技能士へとステップアップしていく制度が整備されています。
厚生労働省の調査結果では、「キャリアコンサルタントとの相談が役に立った」と回答する人が9割に達しており、
この職業の社会的価値の高さが証明されています。
令和3年3月29日に策定された第11次職業能力開発基本計画(令和3年度〜令和7年度)の背景にあるのは、
新型コロナウイルス感染症の影響によるデジタル技術の社会実装の進展、労働市場の不確実性の高まり、
人生100年時代の到来による労働者の職業人生の長期化。
これらの変化に対応するため、企業における人材育成支援と労働者の主体的なキャリア形成支援を両輪とする人材育成戦略が示されました。
セルフ・キャリアドックは、まさにこの戦略の中核を成しています。
セルフ・キャリアドックの導入と定着が重点項目として掲げられているのも頷けます。
企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、
体系的・定期的に従業員の支援を実施する総合的な取り組み。
年齢や昇進などのキャリアの節目にキャリアコンサルティング面談やキャリア研修などを行い、
従業員のリスキリング支援を含めた主体的なキャリア形成を支援する制度なのです。
和田さんが現在提供している「キャリア課題見える化診断ツール」は注目のシステムです。
内発的動機づけと外発的動機づけのどちらが重要かを判定し、組織の課題を見える化。
経営者向けと従業員向けのアンケートを実施し、そのギャップを視覚化することで、組織の真の課題を浮き彫りにします。
診断ツールで見えた課題に対して、セルフ・キャリアドックを実施。
月1回の個人面談によるメンタル相談と、新入社員向け、シニア向け、中堅向け、管理者向けのキャリア研修を組み合わせた総合的な支援プログラム。
実に体系的なアプローチといえるでしょう。
これからの時代、組織は単に人を雇うのではなく、共に成長するパートナーシップを築いていく必要があります。
和田さんが金沢を拠点に展開する診断ツールとキャリア支援システムは、まさにそんな未来の組織づくりを実現する具体的な道筋。
人材定着や組織の課題を抱える企業にとって、和田さんへの相談は新たな可能性を開く第一歩となるに違いありません。
懇親会
今回もセミナー後に懇親会を行いました。その一幕をご紹介いたします。











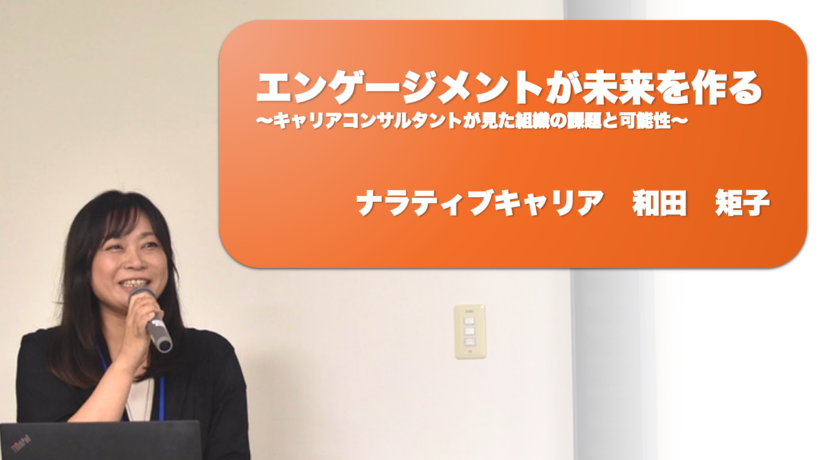






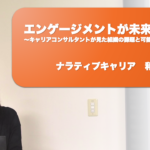
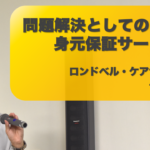
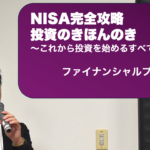




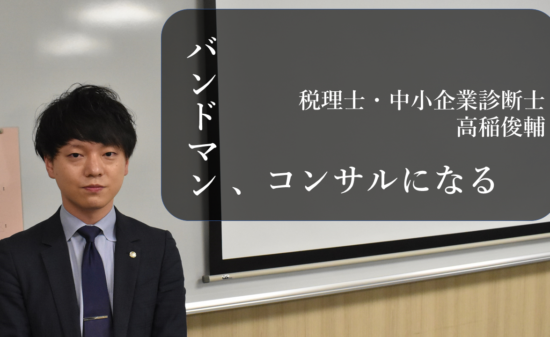
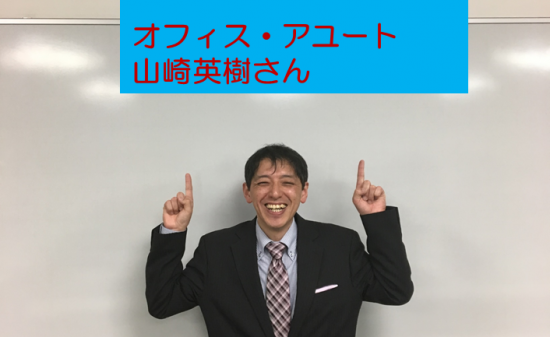






 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。