6月度のKCG定例セミナーの講師は、MRO北陸放送で報道に携わる大西宏和(おおにし ひろかず)さんです。
「アナタの知らないTVの世界」と題してご講演いただきました。
1978年生まれの大西さんは、高岡中学、泉丘高校、金沢大学・大学院を経て2003年にMRO入社。現在は中小企業診断士の資格も持つ多彩な方です。
プライベートでは月200キロのランニングを続けるスポーツマンで、奥様と大学生の息子さんとの3人家族。
そんな大西さんが語る放送業界の実情は、私たちの想像を超えるものでした。

テレビマンの素顔
「テレビマンはかっこよくないとダメだよ」-大西さんが新人時代に先輩から言われたという言葉が印象的でした。
だからこそ現場では「素人が見てもこの人が仕切っているとわかる立ち振る舞い」が求められるのだといいます。
MRO北陸放送は1952年開局の老舗局で、従業員90人、売上38億円を誇ります。
しかし、その裏側では様々な課題と向き合っているのが現実です。
大西さんは「業界の慣性を打破するチャンス」と「ニュースの質への意識向上」をキーワードに、
業界の現状を率直に語ってくださいました。

ニュース制作の舞台裏
普段何気なく見ているニュースが、どのような過程を経て私たちの元に届くのか。その製作工程は実に緻密です。
まず放送局に届く情報の選定から始まり、デスクが取材価値を判断。
その後、記者による徹底したリサーチが行われます。
「本当か嘘か、フェイクじゃないかどうか」を必ず複数の情報源で確認するのが鉄則だといいます。
特に重要事件では「3方向から確認が取れないと出せない」という厳格なルールを設けているそうです。
取材後は原稿執筆、編集、そして放送へと続きます。
通常のニュースは1分から1分半で、原稿は30分もあれば書けるというスピード感。
しかし、その背景には多くのスタッフが関わる複雑な連携システムがあります。
「ネットに溢れている情報とは質が違う」と大西さんは強調します。
「国に認定された放送局がちゃんと調べて出す」情報の信頼性は、コロナ禍でも民放テレビが最も役立つ情報源として評価されたことで証明されました。

能登半島地震での取材体験
昨年の能登半島地震では、MRO北陸放送の真価が試されました。
元日16時06分の緊急地震速報から、わずか4分後の16時10分には通常番組を打ち切り、報道特番に切り替えたスピード対応。
その後、翌日深夜1時25分まで9時間にわたってCMなしで報道を続けました。
特に印象的だったのは、全国からの応援体制です。
系列17局からのべ1200人以上のスタッフが41日間にわたって石川県入りし、取材活動を支援。
被災地への物資輸送では、輪島まで6時間、珠洲まで7時間かけて燃料や食料を運び続けました。
現地の取材班は2泊3日のローテーションで活動。物資保管車と仮眠車を配備し、簡易トイレや非常食を完備した過酷な環境での取材活動でした。
大西さんが監修した特別番組では、被災地出身の若い記者が故郷の現実と向き合う姿が描かれました。
「悲しい思いをした人にマイクを向けるのは、気が引ける」と大西さん。しかし、それこそが「届かない声を届けていく」報道の使命なのだといいます。

テレビ業界の経営構造
「斜陽産業」と言われることもある放送業界ですが、その実態はどうなのでしょうか。
大西さんは収益構造を詳しく解説してくださいました。
MRO北陸放送の収入源は、テレビが圧倒的に多く、ラジオやその他事業がごく一部となっています。
テレビ収入の中でも「ネット」と呼ばれるキー局からの収入が重要な位置を占めています。
これは、TBSなどキー局が全国放送のために地方局の電波使用権を「購入」するシステムによるもの。
視聴率の重要性についても興味深い説明がありました。
視聴率1%の差が収入に与える影響は想像以上に大きく、
「視聴率5%×2万本」と「視聴率7%×2万本」では、同じ本数でも4万パーセント分の売上差が生まれるといいます。
インターネット広告の成長により、確かにテレビ広告は減少傾向にありますが、
「テレビが斜陽というよりも、インターネットが増えている」というのが大西さんの見解。
業界もNEWS DIGやTVerなどのデジタル展開に力を入れており、これらの広告収入は毎年2桁成長を続けているそうです。

若き記者たちの挑戦
印象的だったのは、災害廃棄物仮置き場の閉鎖を取材した若い女性記者のエピソードです。
予定より早く受付を終了し、住民から苦情が出た問題を取材後、「普段すごい静かな子」がその足で市役所に直談判に向かったといいます。
その結果、市長の謝罪コメントが発表され、新たな仮置き場が設置されるという実質的な改善につながりました。
これこそが「困っている人の声、届かない声を広く届けていく」報道の真骨頂だと大西さんは語ります。
現在、MRO北陸放送の3年以内離職率は0%。若い記者たちがやりがいを持って働いている証拠だといいます。
求める人材像として、「打たれ強いこと」「最後までやり抜くこと」「誠実で真摯であること」を挙げる大西さん。
何より「人に対しても、取材対象に対しても、ちゃんと向き合っていける人間」を求めているそうです。

信頼こそが放送局のブランド
講演の最後に、大西さんは「『信頼』こそが私たちのブランド」と強調されました。
ネット時代だからこそ、国に認定された放送局が責任を持って発信する情報の価値は高まっているのかもしれません。
「業界の慣性を打破するチャンス」「ニュースの質への意識向上」という変革の時代にあって、
地域に根ざした放送局の役割はますます重要になってきています。被災地での取材経験を通じて、
改めて地域メディアの使命を再確認したという大西さんの言葉が印象に残りました。
テレビの向こう側で起きている様々な出来事、そこで働く人々の思い、
そして業界が直面する課題と可能性について、貴重なお話を聞かせていただきました。
次回のセミナーも、きっと私たちの知らない世界の扉を開いてくれることでしょう。

懇親会
今回も、定例セミナーの後、懇親会が開かれました。その一幕をご紹介します。












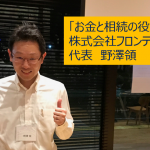
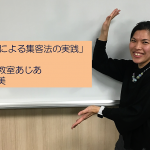



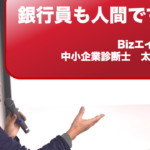
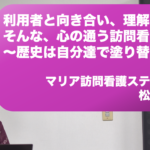
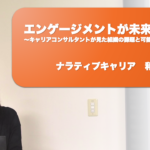
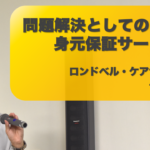
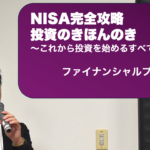
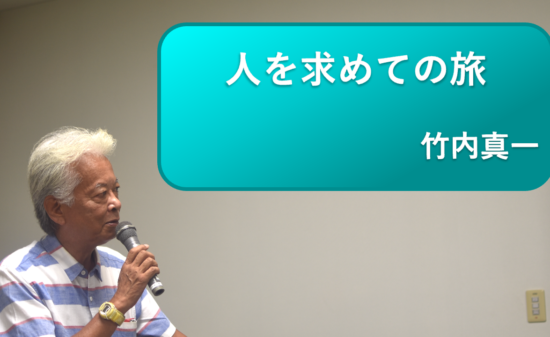
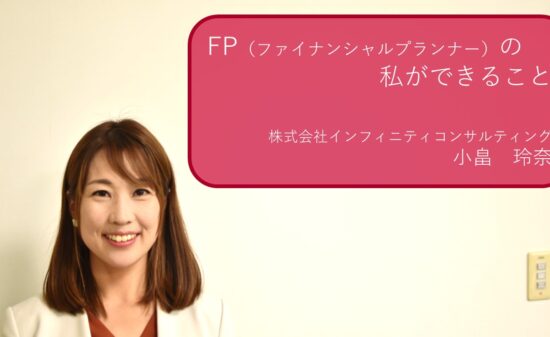

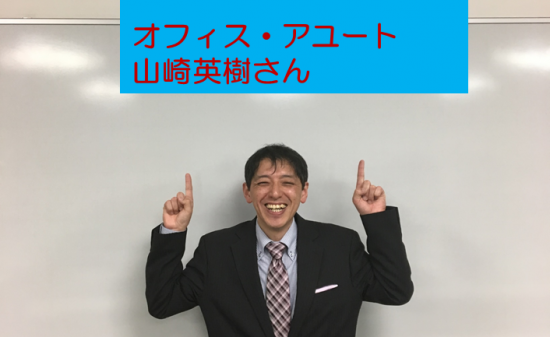


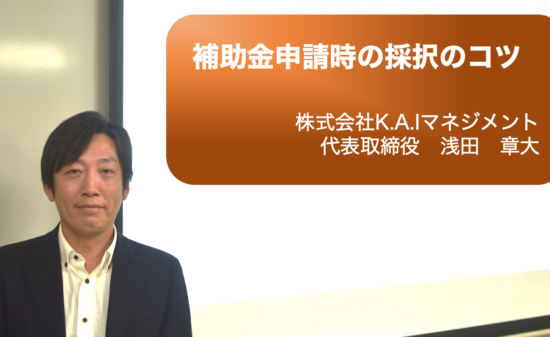
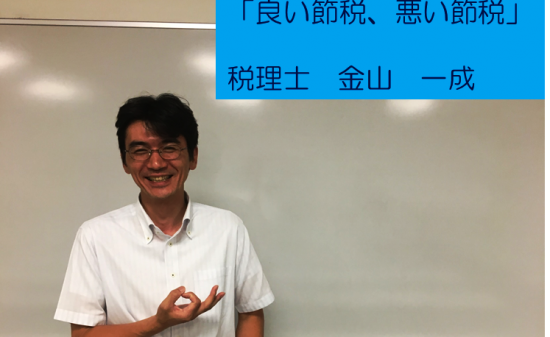


 PAGE TOP
PAGE TOP
この記事へのコメントはありません。